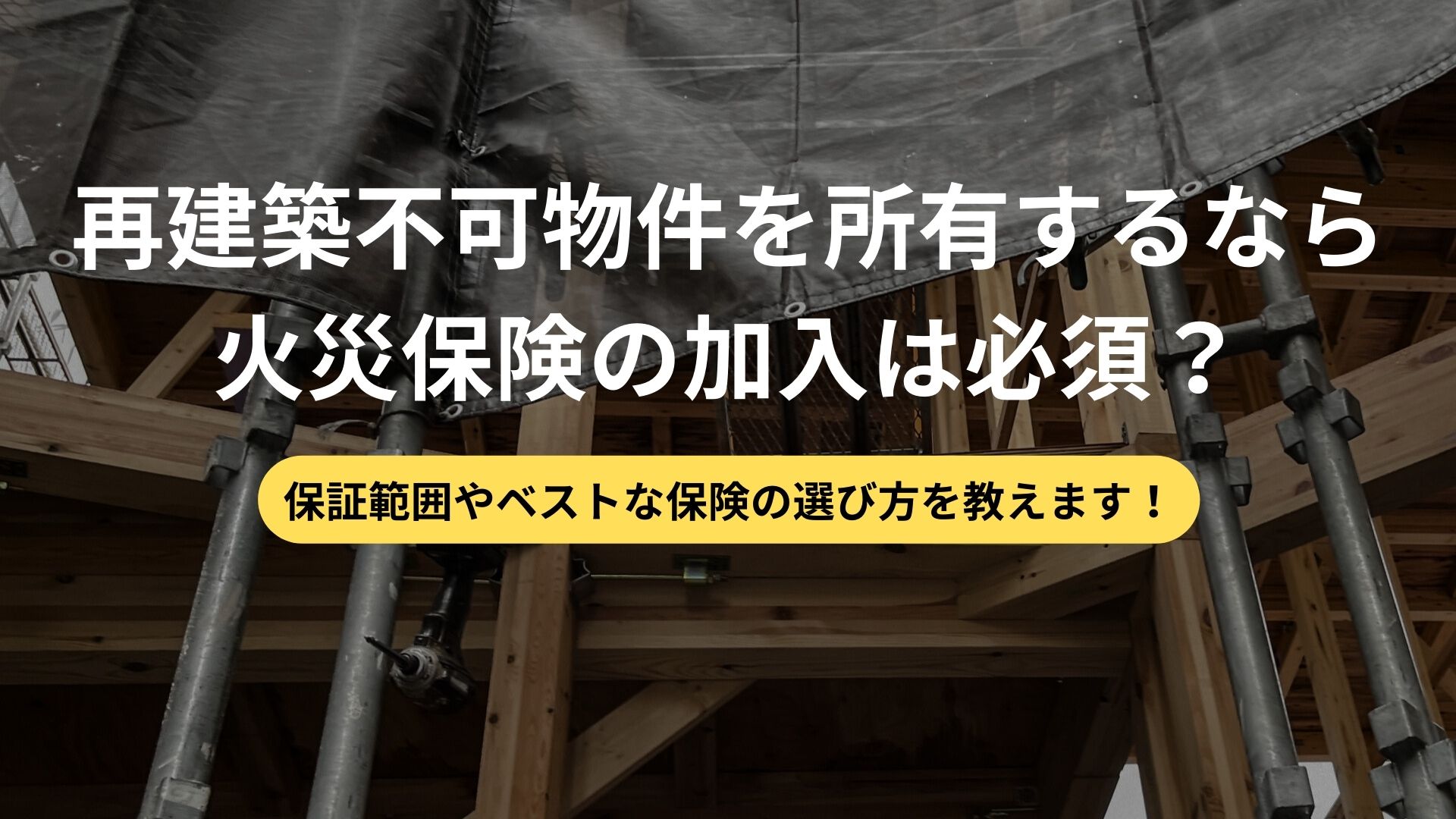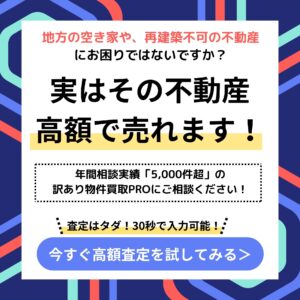「法令に適合してなくて建て替えのできない再建築不可物件でも、火災保険に加入できる?」
結論、建築基準法などの法令に適合せず、新たな建物が建てられない「再建築不可物件」でも、火災保険に加入できます。
「活用せず放置しているけど、火災保険って入る必要あるのだろうか?」という方がいるかもしれません。しかし、再建築不可物件は築年数が古い傾向があり、火災のリスクは通常の不動産よりも高く、火災保険に加入しておかないと金銭的なリスクが発生します。
そこでこの記事では、以下の内容をわかりやすく解説します。
- 再建築不可物件を火災保険に加入しておく必要性
- 火災保険で補償される損害の範囲
- 再建築不可物件の火災保険の選び方
この記事を読んでいただければ、保険加入の必要性を正しく認識した上で、あなたに合った火災保険を選べます。
ちなみに、保険料を払っても活用する余地がない再建築不可物件は、専門の不動産買取業者に相談して売却してしまうのが得策です。
当サイトがおすすめしている「訳あり物件買取プロ」では、一般の不動産屋では取り扱いを断られてしまう再建築不可物件でも高額で売却できます。以下のフォームから無料で相談できるので、気軽に連絡してみてください。
\【高額査定を強化中!】このタイミングで金額を調べておこう!/
>>【たった30秒で入力完了!】
無料で訳あり不動産の高額査定を試す
再建築不可物件でも火災保険に加入できる
たとえ建物が再建築できない状態でも、土地に建物があれば、保険に加入することができます。
保険会社は、保険契約を受け入れるかどうかを、建物の構造、建物の建設年数、そして建物の状態などに基づいて判断します。その判断基準には、建物が再建築可能かどうかや、接道義務を果たしているかどうかは関係ありません。
ただし、建物の状態によっては、保険に加入できない場合もあります。しかし、建物が再建築できないことを理由にして、保険会社から契約を断られたり、高額な保険料を請求されたりすることはありません。
再建築不可物件は火災保険に加入しておくべき
一戸建ての所有者の中には、保険料を節約しようとして、損害保険に入らない人もいます。しかし、再建築不可の物件に関しては、これは非常に高いリスクを伴う選択です。
再建築不可物件を火災保険に加入しておくべき理由は、以下の4点です。
- 築年数が古く火災リスクが高い傾向がある
- 火災時の金銭負担が非常に大きい
- 火災の被害は隣家にも及ぶ恐れがある
- 家屋の評価が低くても、受け取れる保険金は変わらない
築年数が古く火災リスクが高い傾向がある
再建築不可物件は、通常の中古住宅と比べて火災のリスクが高いと言えます。これらの物件は、大部分が昭和25年の建築基準法改正前に建てられた木造住宅です。耐火リフォームを受けていない場合、火災の発生や拡大がしやすくなってしまいます。
さらに、保険に入っていない場合、近隣の家からの火災で自宅が焼失した場合でも、火元の住民は失火責任法の規定により責任免除され、損害賠償を受けることはできません。つまり、修繕費用は全て自己負担となります。
放火や近隣の火事など、火災リスクを完全にゼロにすることは難しいですが、万一の火災に備えるためには保険が不可欠です。そのような状況に備えて、保険に加入することが賢明です。
火災時の金銭負担が非常に大きい
再建築不可物件は、通常の住宅と比べて、火災後の経済的な負担が大きくなるリスクが高いです。
なぜなら、建築基準法により、同じ土地に再建することができず、別の土地を購入して新しい住宅を建てる必要があるからです。新しい住宅を購入する場合、建物の建設費用だけでなく、土地の購入費用もかかります。
このため、再建築不可物件で火災が発生した場合、かなりの負担が予想されます。そのため、保険に加入せずに住み続けることはおすすめできません。
火災の被害は隣家にも及ぶ恐れがある
再建築不可物件は、通常の住宅よりも土地の有効活用を優先し、建物が非常に密集して建てられることがよくあります。さらに、これらの物件は築年数が経過しており、現行の建築基準法で要求される耐火性や耐震構造などの規定を満たしていない場合が多いです。
その結果、火災や火事が発生し、住宅が倒壊すると、隣接する建物にも影響を及ぼし、火が広がって周辺の建物が倒壊し全焼する可能性が高まります。
こうした通常の物件よりも高いリスクを抱えている再建築不可物件では、火災や地震などの災害に備えるために、各種保険に加入することが非常に重要です。将来の不測の事態に備え、保険を検討することが賢明です。
家屋の評価が低くても、受け取れる保険金は変わらない
通常、再建築不可物件は一般的な中古住宅と比べて評価額が低いことがあり、そのために保険金が減少するのではないかと不安に感じる方もいます。
しかし、保険金の支払い額は契約内容と支払った保険料に基づいて決まります。つまり、建物の評価額が低くても、適切な保険料を支払っていれば、十分な補償を受けることができます。
建物が古いまたは価値が低いという点で心配するかもしれませんが、再建築不可物件でも、契約時に設定した保険金を満額受け取ることができるので、安心してください。保険料をしっかり支払い、適切な保険プランを選ぶことが重要です。
火災保険・地震保険で補償される範囲
火災保険・地震保険で補償される損害の範囲を解説します。保証範囲は保険会社によりまちまちです。加入する際はしっかりと保険会社に確認してから加入するようにしましょう。
火災保険で補償される内容
火災や地震保険などの保険に加入する際、補償内容を理解することは重要です。以下に、火災保険の補償範囲と損害支払いのケースを要約しました。
【メインの補償項目】
- 火災
- 落雷
- 爆発や破裂
- 風災
- 雹災や雪災
各保険会社やプランには微妙な違いがありますが、一般的には上記の項目を中心に補償が提供されています。
【一部の保険で追加できる補償項目】
- 水災
- 建物外での物体の落下、飛来、衝突
- 騒擾(デモ行為などによる破損被害)
- 破損や汚損
各社のプランによって、これらの追加項目が含まれることがあります。保険を選ぶ際には、補償内容を確認し、自身のニーズに合ったプランを選ぶことが大切です。
地震保険で保障される内容
地震保険は、地震、噴火、津波による損害をカバーする損害保険の一種です。さらに、この保険には「地震による火災」も含まれています。具体的な補償内容と支払われるケースを以下にまとめました。
- 地震による建物や家財の損壊
- 地震が原因で発生した火災や津波による損害
再建築不可物件の火災保険を選ぶポイント
再建築不可物件の火災保険を選ぶポイントは以下の2点です。
- 予算に合った保険料から選ぶ
- 地震保険を付帯するかどうかを選ぶ
自身の求めている保証範囲、予算と合わない火災保険を選んでしまうと、思わぬ後悔につながりますのでこれから解説するポイントを押さえましょう。
予算に合った保険料から選ぶ
火災保険の保険料は保険会社によって異なります。予算に合った保険料を見つけるために、複数の会社から見積もりを取りましょう。
高い保険料を支払いたくない人には、保険の補償範囲が狭いプランを選ぶことも考えられます。補償範囲が狭い保険は一般に保険料が低くなります。
例えば、物件が内陸にあり、近くに大きな川などがない場合、水災被害の保険を選ばないこともできます。
地震保険を付帯するかどうかを選ぶ
火災保険を検討する際に、地震保険の追加加入を考慮することが重要です。火災保険は地震や津波による損害をカバーしないため、別途地震保険に加入する必要があります。
日本は地震の多い国であり、多くの人々が火災保険と一緒に地震保険にも加入しています。実際、損害保険料率算出機構のデータによれば、2002年度の付帯率が33.3%だったのが、2022年度には69.9%まで増加しています。これは2倍以上の増加です。
火災保険のタイプによっては、地震保険の加入が必須条件の保険と、任意の保険が選べるものがあります。自身のニーズに合わせて保険を選ぶ際に、地震保険の加入を検討しましょう。
参照:損害保険料率算出機構「地震保険 都道府県別付帯率の推移」
まとめ
この記事では、再建築不可物件の火災保険について、必要性や選び方などを解説してきました。
再建築不可物件は通常の不動産よりも火災のリスクが高いため、所有し続ける場合は、火災保険に加入しておくように心がけましょう。
ただ、火災保険と一口に言っても、保証範囲や保険料は会社によってまちまちですので、あなたに合った保険を選ぶことが重要です。
ちなみに、もし毎年保険料を払い続けても、物件を活用する予定がないのであれば、再建築不可物件専門の不動産買取業者に相談して、売却してしまうのが得策です。
当サイトがおすすめしている「訳あり物件買取プロ」では、一般の不動産屋が取り扱いを断るような再建築不可物件でも高額で買い取ってくれます。以下のフォームから無料の買取査定を受けることができるので、気軽に連絡してみてください。
\【高額査定を強化中!】このタイミングで金額を調べておこう!/